去年、今年と引き続きeleven 2ndのニットを販売しています。
本格的に寒くなった近頃はもっぱら、Tシャツに1枚で暖かいヤクのタートル、もしくはTシャツorカシミアのラウンドネックセーターに厚手のカーディガンを羽織ることが多いです。Tシャツは冬以外は1枚で着れますが、冬にはインナーになるという使い方です。バリエーションが増えてカーディガンの種類がとても多いのですが、特にこの季節におすすめの厚手のカーディガン3選+番外編です。
① Cardigan with Muff PKT
ご購入は→こちら
マフとは毛皮などで作られた筒形の両側から手を入れて温めるための防寒具。それに似たかたちから由来する「マフポケット」が特徴的なニットです。可愛いマフポケットと、目が詰まったメンズっぽい仕上がりが気に入ってます。なんとなく異国の少年がポケットに手を入れて着ているような、古着っぽさも感じさせます。サイズはやや幅広で、重ね着もし易い。ヤク100%で肉厚、非常に暖かくカシミヤのような艶、暖かさとウールのようなボリュームという良いとこ取りで、毛玉ができにくいというのも最高のポイント。襟が付いていることからジャケットのようにも着れるのがお気に入りです。





②Raglan Long Cardigan
ご購入は→こちら
ラムズウール 53% , ウール(ヤク)47%の半分半分。起毛させてフワフワのテクスチャーがいかにも柔らかく、暖かそうな冬の幸せいっぱいのニットです。やはりロングということもありお尻まで隠れるのは圧倒的に暖かさが加わります。このカーディガンが少し変わっているのは、ボタンが付いているものの装飾として付いているだけで実際は閉じずに着るのが正解。すっきりとしたラインを保ってガウンのようにさらっと着てください。ロングコートの下に重ね着は更に良いです。




③Chunky V-neck CD
ご購入は→こちら
こちらは①や②よりもたっぷりのサイズ感で特に身幅が広く、ざっくりと着れるカーディガンです。カラーごとに合わせられた樹脂ボタンの組み合わせもたまりません。昨年は4月まで長く着ていました。こちらは使用感が出てくると良い意味で古着っぽさ(アイビーっぽさ)が増します。ヤク47%のため毛玉も出来にくいのですが、ラムズウールのモコモコ感がこのオーバーサイズのかたちによく似合うのです。細身の男性でも着れるくらいですが基本的に女性用です。ザクザク!っと着てください。


番外編★④New Lettered Cardigan
ご購入は→こちら
Lettered CardiganとはまさにIVY!大好きなアイビー。結局、自分の原型って欧米の伝統的なソレにあるな〜と最近思い返していました。なぜなら雑誌ではなく子ども時代の私は昔の映画を愛し、おしゃれは全て映画から学んでいたからです。そしておじさんセーターと勝手に命名しているのですが、いかにも昭和のお父さんお爺ちゃんが定番で着てそうなかたちでもある。実家にある、化学繊維の似たようなカーディガンを就職するまで大事に着ていました。素材が違うのでこういう可愛いボリュームは無かったけれど、昔から好きなかたちです。時々様子が変わった刺激的な洋服も着たくなりますが、いつでも心の定番にはこういった昔ながらのかたちが存在しています。でも時代は令和だから、素材はバージョンアップで。





他にも種類はたくさんありますが、今のおすすめはこのような感じです。総じて、カーディガンは下に上にと重ね着を楽しむためにある、と断言致しましょう! eleven 2ndの商品ページは→こちら
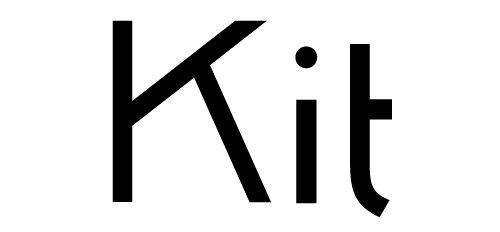


















 おまけ。こちらはとても小さなサイズで携帯用。しかも板は石で出来ています。通りで重いと思った!なんという贅沢品。使用感が出てうっすら紫がかっているのも最高。
おまけ。こちらはとても小さなサイズで携帯用。しかも板は石で出来ています。通りで重いと思った!なんという贅沢品。使用感が出てうっすら紫がかっているのも最高。 この10年間、少ないながらも何度か登場したピッピソン。ピッピ=電話、ソン=線の意味です。
この10年間、少ないながらも何度か登場したピッピソン。ピッピ=電話、ソン=線の意味です。







